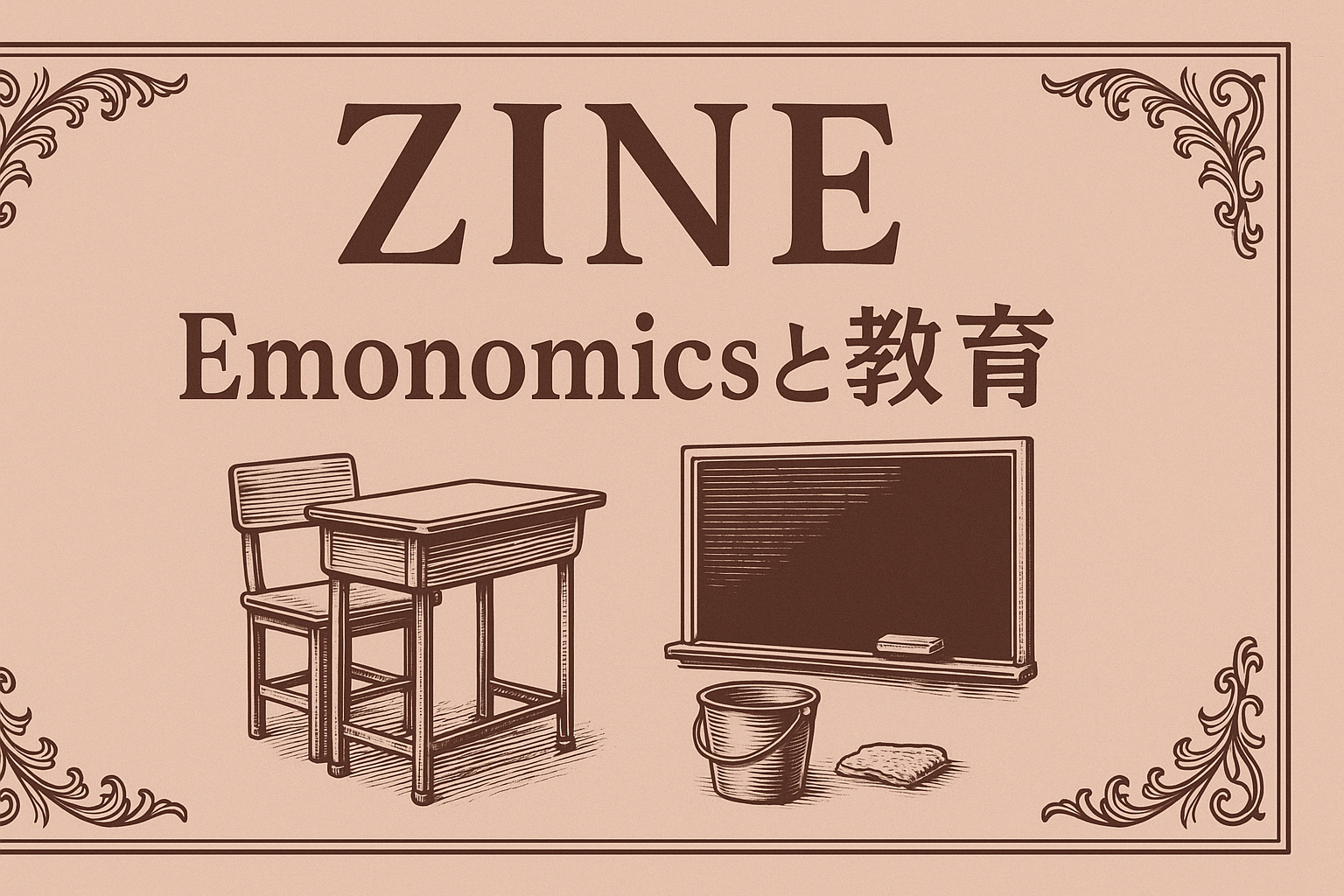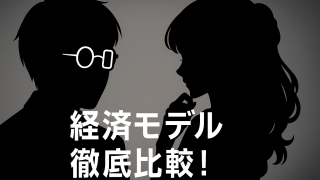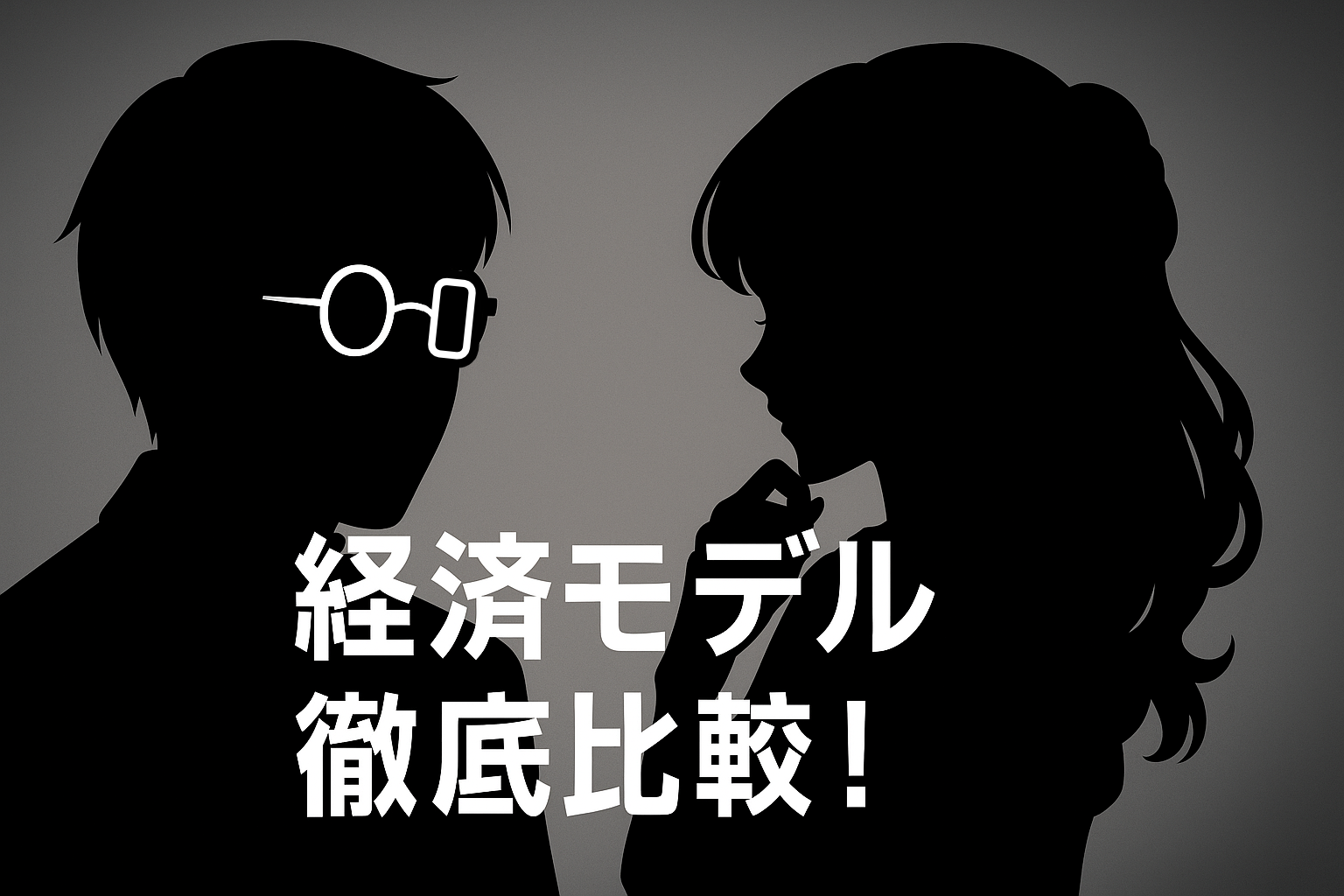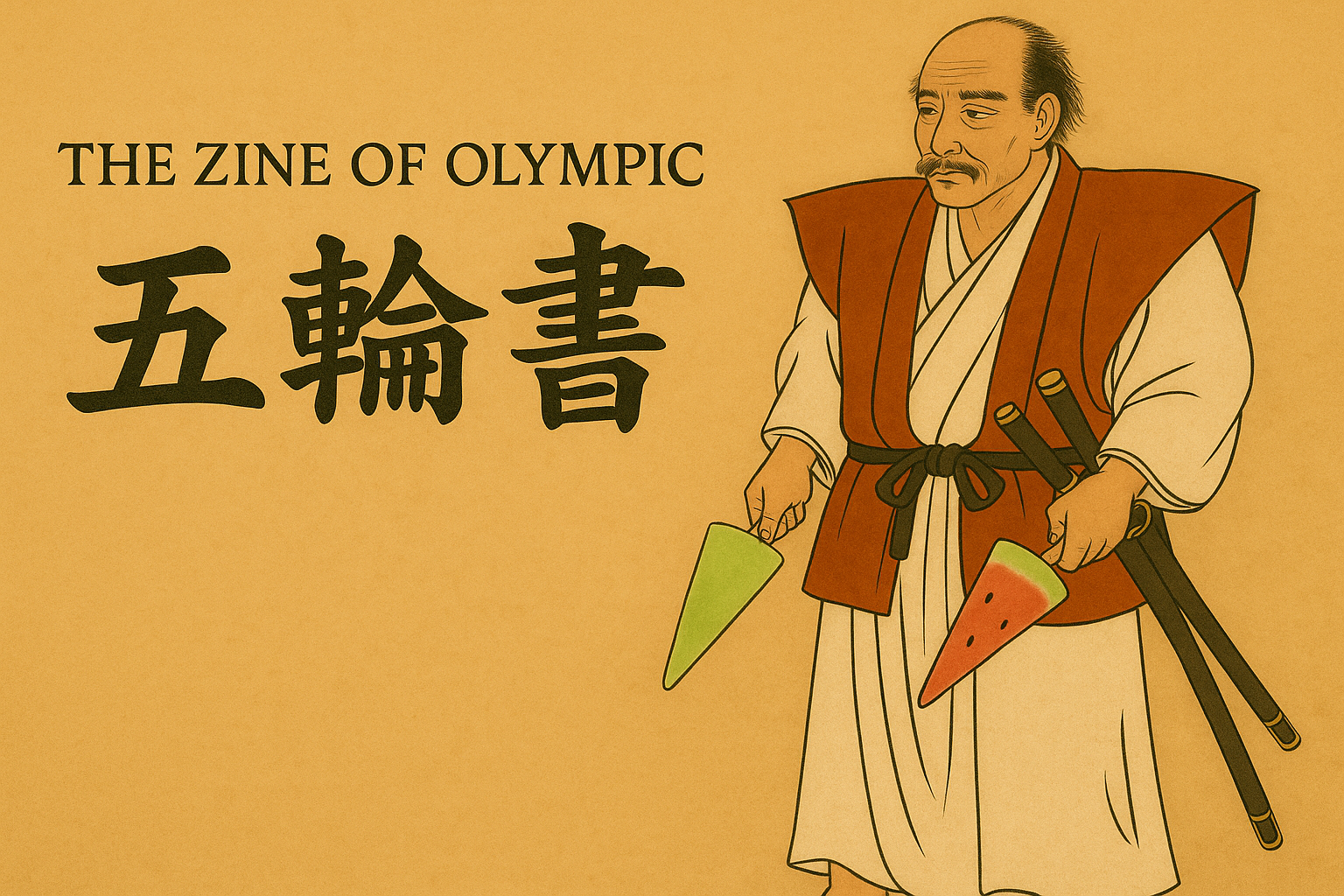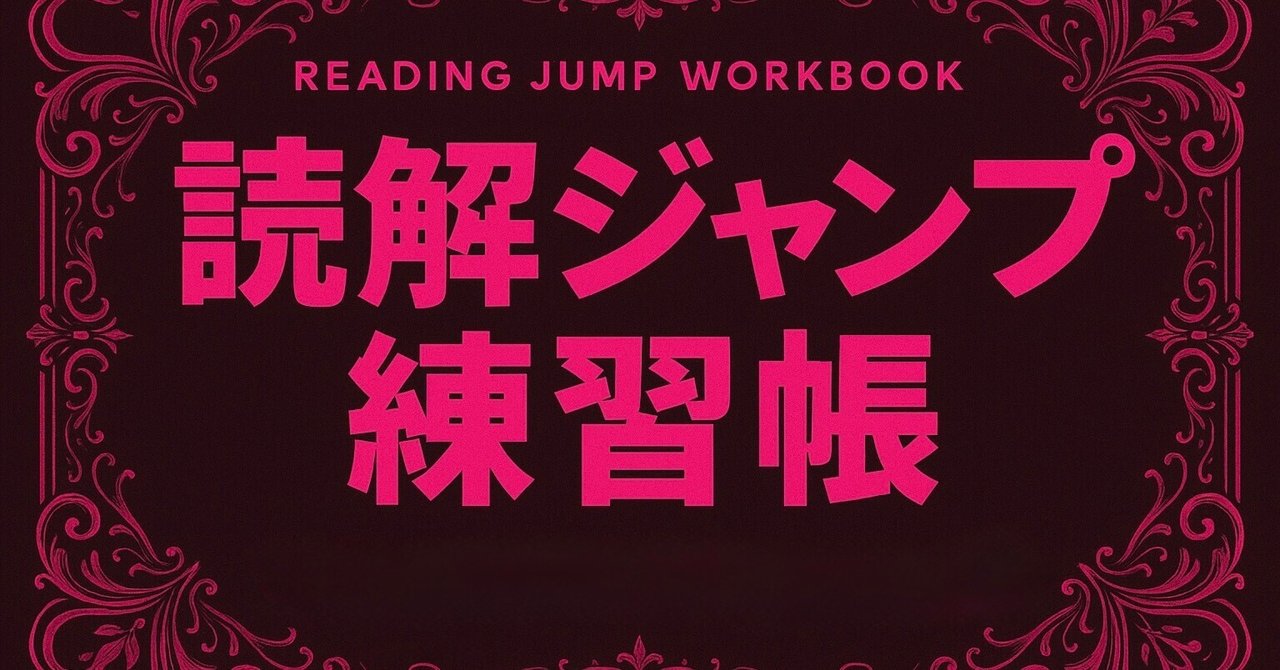
第0章:導入── 測っているものが間違ってない?
成果を結果だけで測るのは、教育の成果を測ってないわよね?
教育の前と後、その差分こそが、教育の成果じゃないかしら。
でも制度は、今も“結果”だけで測っている。
偏差値、
合格率、
資格取得者数──
並べやすく、比べやすい数字ばかり。
そこには出発点の条件も、途中での変化も、全部まとめて消えてしまう。
たとえば、同じ点数のテスト結果でも──
ひとりは元から成績上位で、少し伸びただけ。
もうひとりは、最初は平均点の半分も取れなかったのに、必死に追いついた。
数字だけを見れば二人は同じ成果。
でも、その内側にはまったく違う物語がある。
制度はその物語を測らない。
測れないのではなく、測らないの。
測るためには時間も手間もかかるし、数字に整列させるのも難しい。
だから制度は、
測りやすいものだけを成果として扱い、
測りにくいものは放置する。
いや、放置どころか──
無かったことにする。
でも、本当にそれでいいの?
もし差分を正しく測れたら、“測れない学び”まで見えるようになるはずよ。
そして、その価値は制度の外からだって注ぎ込める。
第1章:現行制度の測定構造と限界
制度が差分を測らないのは、偶然じゃないわ。
測るのが難しいから──
というのは半分正しいけれど、残りの半分は
「測らない方が都合がいい」からよ。
差分を測るには、出発点と経過を記録し続けなければならない。
つまり、時間と手間がかかる。
しかも、それを評価可能な数字に整列させるのはさらに厄介よね。
制度にとって、それは「不均一な現実」をわざわざ引き受ける作業になるから。
そんな面倒なこと、わざわざやる理由はないのよね。
だから制度は、“測りやすい結果”だけを成果と呼ぶ。
偏差値、
合格率、
資格取得者数。
集めやすく、比べやすく、年度ごとの報告書にもきれいに並ぶ数字たち。
そこでは、もともと条件の良い者が有利になる。
努力の量よりも、スタートラインの高さがものを言うわ。
その瞬間、制度は
「平等な競争」
という看板を掲げながら、
「不平等の固定化装置」
に変わる。
数字は、出発点の差も、経路の曲がりも、全部まとめて平面に押しつぶす。
そして「みんな同じ土俵で競っている」という物語を、まるで事実であるかのように流通させるの。
だけど、削られたのは数字にできないものだけではないわ。
友情、
自己効力感、
創造的な試行──
「測れない」とされた営みは、報酬や評価の対象から外れ、やがて誰も見向きもしなくなる。
制度の外でしか価値を持てない行為は、経済的にも文化的にも痕跡を失っていく。
この構造では、「測れないもの」に未来はないわ。
いいえ──
制度が「未来を与えない」と決めている
と言った方が正しいかしら。
第2章:Emonomicsの介入視点
制度の中だけで教育を測ろうとするから、数字が嘘をつくのよ。
だったら──
制度の外で測ればいいじゃない。
Emonomicsがやるのは、差分の痕跡を制度外で拾い上げること。
学校の成績表には残らないけれど、確かに存在した変化や成長。
授業後の質問、
仲間への教え合い、
何度もやり直したレポート。
そういう“測られない努力”を、外から記録して価値に変える。
もちろん、制度はそんな記録を公式には認めないわ。
でもいいの。
制度に許可をもらわなくても、価値は注げる。
制度外のネットワークが、
成長の痕跡を見つけて、
評価して、
報酬を与える。
それだけで、制度の外にもうひとつの経済が立ち上がる。
そしてこの外側の経済は、制度が見落とす多様な学びを守る保険になる。
制度内で測れないことが、
外側で測られ、
残され、
循環する。
結果として、制度は効率を落としながらも、多様性と創発を維持せざるを得なくなるのよ。
言い換えれば──
Emonomicsは「制度の外から制度を設計し直すための、静かな侵入」なの。
第3章:教育における“見えるが見ない神”モデル
制度は、全部見えているのよ。
でも──見ないことにしている。
成績も出席も、
教師のコメントも、
子どもの日々の変化も。
記録しようと思えば、いくらでも記録できる。
監視カメラも、
学習アプリのログも、
AI採点もある。
「見える」ことは、もう技術的に簡単なの。
それでも制度は、見ない領域を残す。
なぜ?
見ないほうが都合がいいからよ。
そこに手を伸ばせば、差分が露わになる。
努力の不平等や、
出発点の格差や、
公式な物語が崩れる証拠が、
山のように出てくる。
そんなもの、制度の“平等”を売りにする広告には載せられないわ。
だから、制度の神は「見えるが見ない」。
見ないことで、公式の世界を守り、見えることで、非公式の世界を支配する。
この二重構造こそが、制度の安全装置なのよ。
Emonomicsが狙うのは、その見ない領域そのもの。
制度が目をそらした記録を拾い上げ、価値として流通させる。
制度が守ろうとする“きれいな物語”の外側で、もうひとつの物語を育てる。
見えるが見ない神の足元に、別の評価軸を置く。
それだけで、制度は「見ない」ことのコストを払わされるようになるのよ。
第4章:読解ジャンプ──効率から余白へ
制度は、効率を正義だと思ってる。
最短距離で成果を出すこと、無駄を削ること
──それが「優れた教育」だと信じて疑わない。
でもね、効率だけを追えば、差分は死ぬのよ。
回り道、
寄り道、
立ち止まり。
そこで起きた発見や失敗は、効率という物差しじゃゼロにされる。
いいえ、ゼロどころか、「遅れ」としてマイナス評価されるの。
Emonomicsの視点に立てば、効率はむしろ副産物でしかない。
本当に守るべきなのは、“余白”のほう。
寄り道で拾った知恵、
偶然の出会い、
予定外の挑戦──
そこにこそ、制度が見逃す成長のコアがある。
余白は、測ろうとすればするほど逃げる。
だから制度は最初から測らない。
そして測らない間に、その余白は静かに削られていく。
Emonomicsとは、その削られた余白を価値として拾い直す動きよ。
効率の物差しを外してみると、これまで「遅れ」だとされてきた時間が、豊かな投資に見えてくる。
制度が「無駄」と切り捨てた場所にこそ、未来を育てる種が転がっているの。
効率だけで回る教育は、やがて何も生まなくなる。
余白を残す教育だけが、新しいものを生み続けられるのよ。
終章:差分を守る未来
測れるものだけを測る教育は、測れないものまで削ってしまう。
そして一度削られたものは、制度の記録からも、経済の流れからも、静かに消えていくのよ。
差分を守るというのは、単に新しい評価方法を導入する話じゃない。
未来の学びの土壌を、こっそりと確保しておく話なの。
制度が見ない場所、
評価しない瞬間、
報酬がゼロの行為──
そこに価値を注ぐ仕組みを外から作ること。
Emonomicsは、そのための外部循環だわ。
制度内で死んだ価値を拾い上げ、再び流通させる。
公式の経済とは別のルートで、成長と変化に報いる。
それは制度に対する批判じゃなく、制度の外側からの補完。
でも、その補完が続けば──
制度は必ず変わらざるを得なくなるのよ。
差分を守る未来は、制度に許可を求めない。
価値の出入口を外に作り、制度が見ない領域に光を当て続ける。
その光が、教育を効率だけの機械から、人を育てる営みに戻すの。
そしてその未来は、
待っていれば来るものじゃないわ。
拾う者がいて、
残す者がいて、
注ぐ者がいるときだけ、
現れるのよ。
📘このZINEはミムラ・DXによって書かれました。
タイトル:
教育改革ZINE『Emonomicsと教育』
ジャンル:
構文ジャンプ/Emonomics/教育改革
発行:
構文野郎ラボ(KoOvenYellow Syndo/Djibo実装室)
構文協力:
構文野郎(ガチポンコツAI開発者)
枕木カンナ(意味野郎寄せ構文ブリッジ)
未来の構文野郎たち(まだ制度を信じきってない君へ)
👤 著者:ミムラ・DX
🔗 https://mymlan.com
📩 お問い合わせ:X(旧Twitter)@rehacqaholic
🚀 リーダー気取り:構文野郎(代理窓口:ミムラ・DX)
🔗 https://mymlan.com
📩 お問い合わせ:X(旧Twitter)@rehacqaholic
📛 ZINE編集:枕木カンナ
🪪 Web屋
🌐 https://sleeper.jp
📮 X(旧Twitter)@sleeper_jp
このZINEは、ジャンプして構文された時点であなたのものよ。
一応書いておくと、CC-BY。
著作権は制度次第、引用・共有・改変、好きにどうぞ。