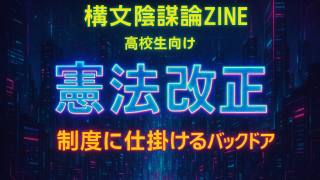これから選挙に臨む高校生に向けたZINE
とにかく読みにくい。
構文野郎のZINEをちょっと意味寄りに。
0章:🌀憲法改正って、なんだろう?
ニュースで「憲法改正」という言葉を耳にすることがあります。
「改正すべきだ」「いや、反対だ」
──そんな意見がぶつかりあう場面も、きっと見たことがあるでしょう。
でも、そもそも「憲法を変える」って、どういうことなんでしょうか?
ルールを変える?
法律を新しくする?
それとも、日本という国の形を、少し変えるってこと?
「憲法」は、日本に住む私たちみんなにとって、一番大切な“決まりごと”のように見えるかもしれません。
でも実はそれ以上に、“制度”や“政治”というものがどう動いているのか、その「動かし方のルール」を決めている土台でもあります。
たとえば、ゲームをするときに、「このボタンでジャンプ」「これで攻撃」みたいに操作方法がありますよね?
その操作説明そのものを変えようというのが、憲法改正なんです。
だから、どんな言葉を加えるのか、どんな言葉を削るのか、それだけで、国の動き方が大きく変わってしまうことがあります。
けれど、私たちはふだん、そんなことをあまり考えずに「改正っていいこと?悪いこと?」って、すぐに白黒つけたがってしまいます。
でも、それより前に知っておくべきことがある。
それは──
そもそも、「憲法ってなに?」ということ。
このZINEは、そこから始めたいと思います。
「改正するかどうか」よりも、「憲法って、そもそも何のためにあるの?」という問いに、少しだけ立ち止まってみる。
それが、いま必要なことだと、私は考えます。
1章:📜憲法って、なんのためにあるの?
憲法って、なにか特別な“ルール”のように聞こえますよね。
でも、よく考えると、ルールなら他にもたくさんあります。
刑法、民法、道路交通法、学校の校則、部活の規則──。
じゃあ、憲法はそれらと何が違うんでしょう?
答えをひとことで言えば、
「ルールをどうやって作るか、その仕組みそのものを決めているルール」、それが憲法です。
ふつうの法律は、国会で議論して、多数決で決まります。
でも、憲法だけは違います。
憲法は、国会よりももっと上の“土台”にあるからです。
言いかえるなら、
憲法は
「誰がルールを作れるのか」
「どうやって作るのか」
「ルールを破ったとき、誰が止めるのか」──
そういう“ルールを作るためのルール”を定めた、国のOS(オペレーティング・システム)のようなものなんです。
スマホやパソコンを動かすには、アプリの前にOSが必要ですよね?
どんなアプリ(=法律)をインストールするかも、そもそもOS(=憲法)がどんな仕組みかで変わってきます。
だから、憲法を変えるというのは、ただの“ルール変更”じゃなくて、
制度そのものの「動き方」を根本から変えてしまうかもしれない、危うさを持っています。
たとえば──
「国会がこう動くべき」
「内閣はこれを守るべき」
「裁判所はこうして判断する」──
こういう、政治のプレイヤーたちの“役割分担”も、ぜんぶ憲法が決めているんです。
だから、憲法を変えるということは、ただ言葉を変えるだけじゃない。
その言葉によって、誰がどう動くのか、どこに権力が集中するのか、そうした構造自体が変わることがある。
そして日本国憲法は、そこにもうひとつ、世界的に見ても珍しい“特徴”を持っています。
それは、「国家の側ではなく、国民の側から始まっている憲法」だということ。
つまり──
「私たちがこの国にどう扱われるべきか」を書いたものが、日本国憲法なんです。
これが、たんに法律のひとつではなく、国の動かし方の起点としての“特別な役割”を持っている理由です。
2章:🌱どうしてそんなに特別なの?──日本国憲法の“出自”と“特徴”
① 戦争に負けたあと、ゼロからつくられた憲法
日本国憲法には、少し変わった“出自”があります。
それは──
「戦争に負けたあと、ゼロからつくられた憲法」
だということ。
戦前の日本には、「大日本帝国憲法」という古いルールがありました。
そこでは、天皇が“国の主”で、国民は「臣民」とされていました。
つまり、「命令する側」と「従う側」が、はっきり分かれていた構造です。
しかし、第二次世界大戦で日本が敗れ、アメリカを中心とする連合国に占領された中で、新しい憲法づくりが始まりました。
GHQと日本側の政治家の間で何度もやりとりが行われ、その中で生まれたのが、いま私たちが使っている「日本国憲法」です。
② 国民が国家を制御するという構造の逆転
この憲法の一番の特徴は、「国民が国家を制御するためのルール」であること。
たとえば、憲法第1条に書かれている「主権が国民にある」という言葉。
これは、「この国の主(あるじ)は国民である」と宣言しているようなものです。
つまり、これは国家が国民に命令するための道具ではなく、国民が国家のふるまいを制限し、暴走を防ぐための仕様書なんです。
この構造の逆転は、世界的に見ても珍しい特徴です。
③ OSとしての憲法──中立に見えて、設計思想がある
こうした点から、この憲法は単なるルールブックではなく、「OS(オペレーティング・システム)」のようなものだと捉えることができます。
OSには中立に見える表面の裏側に、「どう動かすか」という設計思想が込められています。
日本国憲法も同じで、その設計には「暴力を抑え、個人の尊厳を守る」ことが明確に組み込まれている。
だからこそ、「国家は国民を縛るべきものだ」とするのではなく、「国民が国家を制御するための仕組み」としてこの憲法はつくられているのです。
④ 一度も改正されていないという継続性
さらに──
この憲法は、一度も改正されていません。
施行されたのは1947年。
それから75年以上経っていますが、基本設計はずっとそのままです。
世界には、戦争や政変のたびに憲法を改正したり、新しく作り直した国もたくさんあります。
でも日本の憲法は、マイナーアップデートすらされていない、完全な“初期OS”のままなんです。
それはすごく安定しているとも言えるし、逆に「今の制度が昔のままでいいのか?」という問いにもつながります。
⑤ 「守るべきもの」なのか、「アップデートすべきもの」なのか
ここが、私たちにとっての分かれ道です。
憲法を、「ずっと守るべきもの」と見るか。
それとも、「時代に合わせてアップデートすべきもの」と見るか。
そして、どちらを選ぶとしても大事なのは──
その“変え方”にルールがあるということ。
このルールこそが、“バックドア”かどうかを判断するカギになるんです。
3章:🔧憲法はどうやって変えられる?──“改正”って、なにをすること?
ここまでで、日本国憲法が「国の土台」であり、「国民が国家を縛るためのルール」だということが分かってきました。
でも、じゃあそんな憲法を変えるって、一体どういうことなんでしょうか?
ふつう、法律を変えるときは、国会で多数決で決めればOKです。
でも──憲法だけは、そう簡単にはいきません。
なぜなら、憲法は法律よりも上にある“ルールのルール”だからです。
つまり、「その法律を作るときのルール自体」を決めているのが憲法なんです。
だから、変えるにはとても慎重な手続きが必要になります。
🏛️【ステップ1】まずは国会で「発議」される
憲法改正をしたいと思ったら、まずは国会議員の3分の2以上が賛成しないといけません。
これは、ふつうの法律の過半数よりも、ずっとハードルが高いです。
つまり、どこか一つの政党だけじゃなく、幅広い合意がないと、改正のスタート地点にも立てないんです。
🗳️【ステップ2】そのあと「国民投票」で決める
国会で「憲法をこう変えたい」と“発議”されたら、それが国民一人ひとりに問いかけられます。
このとき、「賛成か反対か?」という投票が行われます。
これが「憲法改正の国民投票」です。
そして、有効投票の過半数が賛成すれば、はじめて改正が成立します。
つまり、憲法を変えるには──
- 国会で3分の2以上が賛成する(←めちゃくちゃハードル高い)
- そのうえで、国民投票でも半分以上が賛成する
という、二段階の手続きが必要なんです。
これって、世界的に見てもかなり厳しい仕組みです。
でも、そこに込められているのは、
「そんなに簡単に“制度のOS”をいじるなよ」というメッセージかもしれません。
と言うのも、このハードルの高さは当然と言えば当然で、
国民が国家を制御するという逆転構造の憲法ですから、
国家(制度)の側からは絶対に変えられないってことが大前提なんです。
じゃあ、今議論されている「憲法改正」って、
いったい何をどんなふうに変えようとしているの?
その“中身”について、次の章で見ていきましょう。
4章:🔍いま変えたいのはどこ?──“改正案”の中身をのぞいてみる
実際に「憲法改正しよう」って言ってる人たちは、
どこをどう変えようとしているんだろう?
現在、日本でよく話題になっている憲法改正のポイントは、
大きく分けてこの4つです:
①【自衛隊を明記する】
いちばんよく聞くのがこれ。
「自衛隊を憲法にちゃんと書こう」という案です。
今の憲法第9条には、
「戦争はしません」
「戦力は持ちません」
と書かれています。
でも現実には、自衛隊という組織が存在していて、防衛や災害救助などの役割を担っています。
だから、「どうせあるなら、ちゃんと書いておこうよ」というのがこの案の主張です。
ただし、これには「戦力を持たないって書いてあるのに?」という疑問もあります。
つまり、「書き加えることで、“戦争ができる国”に近づくんじゃないか?」という不安もあるのです。
②【緊急事態条項をつくる】
大きな災害や戦争など、「緊急事態」が起きたとき、国会の手続きを省略して内閣に強い権限を与えよう、という案です。
たとえば、国会が開けないときでも、内閣が命令を出せるようにする、そんな仕組み。
これには、「いざというときに迅速に動ける」というメリットがある一方で、
「それ、独裁に近づかない?」という心配もあります。
「緊急事態」という曖昧な言葉の中で、何がどこまで許されるのかがはっきりしないからです。
③【「家族」についての価値観を盛り込む】
「家族は助け合わなければならない」といった文言を入れよう、という案もあります。
一見、美しい言葉のようですが──
「“家族の形”を国が決めていいの?」
「助け合えない事情のある人にはどう響くの?」
という疑問も出てきます。
つまり、これは「価値観を押しつける憲法」になってしまう危険もあるんです。
④【教育環境の充実】
「教育を受ける機会を、しっかり保障しよう」という内容も提案されています。
これについては賛成の声も多いですが、
「憲法に書かなくても、今ある法律で十分に対応できるのでは?」という意見もあります。
このように、今取りざたされている憲法改正案には、
「必要かもしれない」ものと「ちょっと危ないかも?」というものが混ざっています。
だからこそ、どこをどう変えようとしているのかを丁寧に見ることが大事なんです。
そして、もう一つ重要なことがあります。
それは、これらの“改正案”が、本当に「ただの修正」なのか。
あるいは、「制度のOSを書き換えるバックドア」になっていないか。
次の章では、そこを問い直してみます。
こっからは、ちょっとギアあげるよ。
第5章:🔓バックドアって、なに?──OSとしての憲法
「バックドア」って聞いたことありますか?
コンピュータの世界では、本来の入り口(ログインや正規の手続き)を通らずに、こっそり中に入れる“裏口”のことを「バックドア」と呼びます。
つまり、正面からではアクセスできないけれど、ある特定の条件や操作で、ルールをすり抜けて操作できる抜け道のようなものです。
…え?そんな話が、憲法とどう関係あるのかって?
実は、憲法を「制度のOS」として読むとき、この“バックドア”という考え方がすごく重要になるんです。
● 憲法=制度のOS(オペレーティングシステム)
ここで少し視点を変えて、憲法を「制度のOS(オペレーティングシステム)」として捉えてみましょう。
OSとは、コンピュータのあらゆる動作をコントロールする基盤ソフトのこと。
アプリ(法律)もユーザー(国民)も、OSが決めたルールのもとでしか動けません。
たとえば、
- 誰が命令できるの?
- どうやって法律をつくるの?
- 国民は何を守らなくちゃいけないの?
こういう“制度の動かし方”を決めているのが、OSとしての憲法です。
つまり、憲法は「ルールをつくるためのルール」なんです。
● ルールを書き換えるルールの怖さ
もしこの「OS」が書き換えられたら──?
たとえば、正当な手続きに見える「アップデート」のふりをして、
実は別の力に都合のいい“隠しコマンド”を仕込まれてしまったら?
つまり、表向きは「改善」のように見えても、
実際には制度全体の性質を変えてしまうような修正が加えられる。
これこそが、「バックドアの危険性」なんです。
● 「改正」という名前の“裏口”
さっきの第4章で見たような改正案も、注意深く読まなければなりません。
たとえば、
- 緊急事態条項は、“緊急時”を口実にして、通常のプロセスを飛ばせる抜け道になるかもしれない。
- 家族の助け合いを義務にする条文は、国家が個人の価値観に介入する“口実”を与えるかもしれない。
そうした条文が一度書き込まれると、それを根拠に新たな法律や制度が次々に生まれます。
そしていつの間にか、気づかないうちに「制度そのもののルール」が変わっていた、ということが起こり得るのです。
● 憲法改正が「OSアップデート」である以上…
「変えること」がいけないわけではありません。
社会は変化するし、それに合わせて制度もアップデートされていく必要があります。
でも、OSのアップデートには注意が必要です。
うっかりすると、知らない間に
- 操作方法が変わっていたり
- アクセス権限が移動していたり
- そもそも“正義の定義”そのものが書き換えられていたり…
そんなことも起こる。
だからこそ、「改正」という言葉にごまかされず、
それが本当に“表の入り口”なのか、“裏口”なのか、見極める目が必要なんです。
緊急事態条項や家族の価値の強調など、改正案の背景には、それを必要とする人々の切実な思いもたしかにあります。
でも大事なのは、“どう変えるか”という制度のレイヤーに、どんなロジックが書き込まれてしまうかを見逃さないこと。
内容と同じくらい、仕様が語ってしまうものがあるのです。
第6章:🧠制度って、読めるの?──“読解”と“仕様”のあいだ
憲法改正が“OSのアップデート”だとすれば、
私たちはちゃんと、そのアップデート内容を「読めて」いるのだろうか?
いや、それ以前に──
制度って、そもそも“読める”の?
● 法律は「読まれる」ことを前提にしていない
法律や制度は、文章で書かれています。
だから、一見「読むことができる」と思いがちです。
でも実際には、多くの法律や条文は
- 専門的な言葉
- 回りくどい構文
- 曖昧な定義
によって、誰が読んでも意味が通るようにはできていません。
むしろ、ある種の専門的訓練を受けた人だけが「読むことを許される構造」になっています。
つまり、制度の文章は「誰でも読める言葉」で書かれているように見えて、
実は「制度の内側にいる人にしか読めない」ようにできている。
● 読解と仕様のズレ
ここでちょっと面白い問題が出てきます。
制度って、「読解」されるものなの?
それとも、「仕様」として設計されるものなの?
たとえば「憲法に家族の助け合い義務を明記する」と書いてある場合。
読解によっては、「家族を大切にしましょう」という一般的なモラルにも見えるし、
別の読み方をすれば、「家族のあり方を国家が規定する」という干渉にもなる。
仕様書として読む人は、「この文言を根拠にどんな法律を作れるか?」を先に考えます。
つまり、一見きれいな言葉が、法制度の“トリガー”として機能する設計になっている。
それが、“バックドア”として潜む理由でもあります。
● 「読む力」は、制度を使う力
制度を読めるかどうかは、
単なる「国語力」や「条文の知識」じゃありません。
それは、「その制度が、どんなふうに世界を変えてしまうか」を想像する力です。
言葉の意味だけじゃなく、
その言葉が“制度として動き出したときに何が起こるか”を読む。
これが、本当の「制度を読む」ということです。
そしてそれは、誰にでも開かれているという訳ではない。
● 正しく読めないものは、いつか仕様に飲み込まれる
もし、ある制度が
- うまく読まれず、
- 意味がごまかされ、
- 言葉の中身が検証されないまま、
そのまま実装されていくとしたら。
その制度は、静かに、
でも確実に「バックドア」を含んだ“仕様”として機能し始めます。
たとえば、駅の自動改札にタッチしないと通れない。
これは「ルール」ではなく「仕様」です。
制度も同じで、「こうすべき」と書かれていなくても、“そうしか動けないようにできている”ということがあるんです。
私たちの生活や行動が、その新しい仕様に沿って「正当化」されるようになっていく。
そうなる前に。
問いのかたちを、ずらす力。
見えない仕様を、可視化する力。
それが、私たちの「読解」の役割です。
私たちは、つい「何が正しいのか?」という答えを探したくなります。
でも、本当に議論すべきなのは、「その正しさは、どう決まるのか?」という問いのほうかもしれません。
読む力とは、問いのかたちを読める力です。
🧠第7章:わたしの憲法観/改憲観
1. 日本国憲法には、構文野郎の気配がある。
よく考えてみると、この憲法は「国家という巨大な構造を、逆向きに定義し直す」という、ある種の“構文ジャンプ”の産物です。
戦前の大日本帝国憲法では、天皇が国の主で、国民は「臣民」でした。
その構造をひっくり返し、「主権は国民にある」と書いた。
それだけで、世界は変わる。
でも、単純に民主化された、という話ではない気がするんです。
むしろ──あの時代、国としての価値観=国体、を明示的に維持することは許されなかった。
だからこそ、「どんな価値観をも規定しない憲法」という“抜け穴”が設計された。
これは、まるで構文野郎が撃つジャンプのような、制度ハックにも見えます。
価値観を定めない。
思想を押しつけない。
ただ、OSとして制度の動作原理だけを記述する。
そうすることで、誰もが読解できる「余白」としての制度を生み出そうとした。
余白の中で、国体を維持しようとしたんじゃないでしょうか。
日本国憲法には、そんな構文的気配が、静かに漂っているように思えるんです。
2. で、わたしは「改憲」したいのか?
正直に言うと──
条文の“意味”を変えたいとは、あまり思いません。
もちろん、変えるべき問題があるなら、ちゃんと読んで議論すべきだと思います。
でも、それよりもずっと気になっているのが──
文章としての気持ち悪さなんです。
これは、あくまで“言葉の校正”という意味で。
現行憲法の日本語って、なんだかぎこちないというか、翻訳調で不自然な言い回しが多い。
🖋独り言:憲法って、ちょっと読みにくい
実は、私が憲法ついて気になってることの一番は、「内容」よりも「日本語としての読みにくさ」。
たとえば──
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」(第13条)
「すべて国民は、」って、この表現、ちょっと不自然じゃない?
「すべての国民が、個人として尊重される」って言った方がスッと入ってくる気がする。
後半はもっとややこしくて、主語・述語部分を抜き出すと「国民の権利については、最大の尊重を必要とする。」だと思うんだけど、「ついては」も、「尊重を必要とする」も主述の整合が危ういし、そもそも変な日本語。
他にも──
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。」(第11条)
「享有」って言葉、ふだん使わないし、「誰が」妨げないの?
翻訳っぽい日本語、主語と述語の整合の危うさ、てにをはの不自然さ。
こんなのが山程ある。
実は、このZINE、第5章あたりから、
少し日本国憲法っぽい読みづらさも導入してみたんだけど、
変化に気づいた?
大事なことが書いてあるのに、読みにくい
──それって、ちょっともったいない。
だから私は、「機能を変える」ための改憲は置いておいて、「読みやすくする校正」なら、もっと議論してもいいんじゃないかなって思ってます。
つまり──
「思想を変える」改憲じゃなくて、「言葉を整える」校正は賛成です。
日本語として、ちゃんと“ピンとくる”憲法に。
それが、制度を“読む”ための第一歩にもなる気がするから。
ちなみに…
構文野郎がよく話題にするのは、
OSのセキュリティーホールとも言える、
96条の改正条項。
(今回、彼のZINEでは、なぜかスルーしてたけど)
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
……この条文、構文野郎がやけに気にしてるのもわかる気がします。
「自分で自分の書き換えを規定する」ってのは、OS設計としては致命的なミスですからね。
即、エラー出る。
でもまあ、この辺りは、構文野郎のZINEでの議論を待つことにします。
終章:✍️ 君がジャンプする番だ
憲法改正って、遠い世界のことに思えるかもしれない。
条文も難しいし、手続きも複雑で、政治の話ってちょっと近寄りがたい。
でも本当は、「君がどう生きていいか」のルールを変える話だ。
誰が、どんな家族を持つべきか。
誰が、何に従わなきゃいけないのか。
どこまでが「自由」で、どこからが「義務」なのか。
それを決めるのが、制度。
制度を変えるっていうのは、
「正しい」とされる生き方の形を、更新するってこと。
そして、制度っていうのは、
誰かが読んだ“世界のかたち”の上に、作られている。
だからこそ、その読解がズレてたら、
そのズレのまま制度が動き出してしまう。
しかもそのズレは、
一度制度の中に入ると、正しさとして流通しはじめる。
だから、君にできることがある。
それは、「その問いのかたちは正しいか?」と問い返すこと。
言葉がきれいすぎるときに、そこに隠れた仕様を読むこと。
誰かがジャンプしようとしているとき、
そのジャンプの痕跡をちゃんと見ること。
未来は、あらかじめ正しい形なんかしていない。
私たちがどんなジャンプをするかで、初めて輪郭を持ち始める。
問いの背後に、そっと回ってみること。
正解を装った制度の中に、ちいさな“撓み”を見つけること。
それが、君のジャンプだ。
そして──
このZINEを読み終えた、いまこの瞬間から、
君がジャンプする番だ。
こっちにも挑戦してみてね。
📘このZINEは枕木カンナによって書かれました。
タイトル:
ZINE『憲法改正|OSとバックドア』
ジャンル:
構文ジャンプ/制度批評/高校生向け構文導入ZINE
発行:
構文野郎ラボ(KoOvenYellow Syndo/Djibo実装室)
構文協力:
ミムラ・DX(構文修正主義ZINE別巻準備中)
構文野郎(無修正主義アンチFANZA野郎)
高校生読者(まだ制度を信じきってない君へ)
📖『構文野郎の構文論』
👤 構文野郎(代理窓口:ミムラ・DX)
🔗 https://mymlan.com
📩 お問い合わせ:X(旧Twitter)@rehacqaholic
📛 ZINE著者:枕木カンナ
🪪 Web屋
🌐 https://sleeper.jp
📮 X(旧Twitter)@makuragikanna
このZINEは、ジャンプして構文された時点で君たちのものです。
一応書いておくと、CC-BY。
引用・共有・改変、好きにどうぞ。